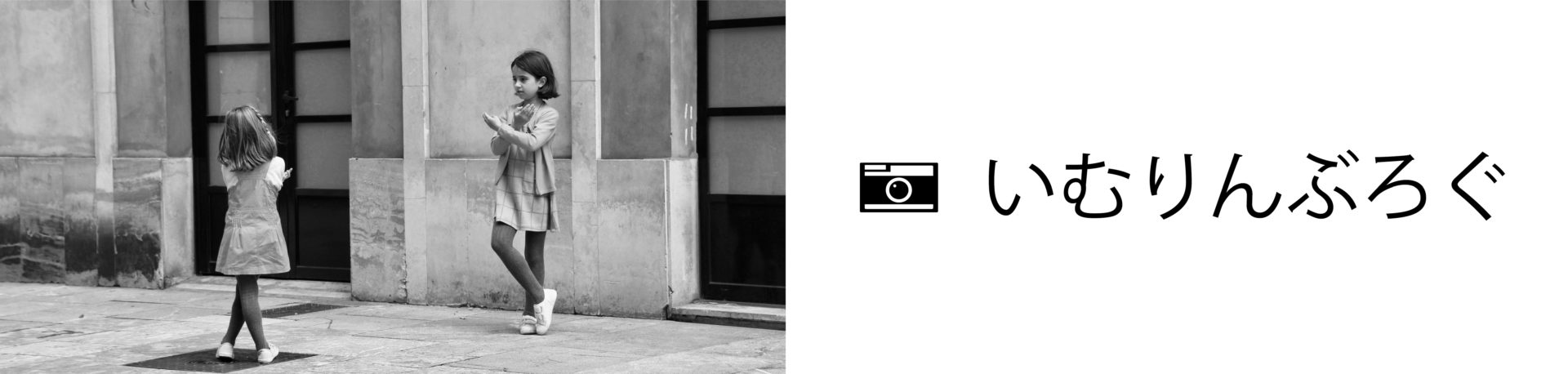久しぶりのブログ更新。写真作家とは何かを考える機会に恵まれたので。今回伺った内容と今の自分の解釈を絡めて、芸術作品としての写真とは何か、作家とは何なのかを残しておこうと思う。
誰もが写真を撮れる時代の写真家とは
PC画面から顔を上げるだけで幾つかの写真が勝手に目に飛び込んでくる。情報を伝達する媒体として無くてはならない物となった。もはや今、写真を見ずに1日を過ごすことは不可能だ。
また技術の進化は写真を撮るという特別な行為から、食事をするレベルの日常に組み込んでしまった。写真は誰もが撮れる時代になった。きれいな写真、かっこいい写真はインスタグラムを代表とするSNSを中心に、日々生成され続けている。猫も杓子も写真家である。そのような状態から、素人と大家の区別がつきづらい写真は第二芸術の分野に位置づけられる。
ではそんな時代にあって、あえて芸術分野へと進み、写真という表現手段を撮るということはどういうことなのか?作品としての写真を撮るという行為はどうあるべきなのか?こうした軸や信念が写真家の独自のスタイルとなり得ると考える。
単なる写真と作品の違いとは
究極的には自身で作家を名乗り、作品として世に出せば作家の作った作品である。犬の糞でさえ「循環」とかよくわからないようなそれっぽいタイトルをつければ作品である。ただしその作品という言葉をまとった犬の糞の価値は、一体誰が担保するのかという話。担保さえされれば金を出す酔狂な人も現れるかもしれない。
つまり価値が担保されているものがマーケットにおいての作品だといえる。どれだけ大家の作品と言われるものがあってもそれを保証するものがなければ、場合によってはただの紙切れともなり得る。
この価値を担保してくれる人たちに認めてもらえるという行為を経ているかどうかが、写真を作品たらしめているということだと言えるのではないかと思う。
写真は芸術作品となりえるのか
デジタル写真が基本となった今、自宅のハードディスクには写真データがたんまり保管されている。これらは写真ではなく単なる画像データである。(もちろんデジタル上のデータとしての作品もあるが)よく撮れたと思っていても、やっぱり画像データ止まりである。当然だがプリントされて初めて写真となる。
プリントした写真を作品として仕上げて初めて(作品用にプリントしての方が正しいけども)作品となる。
ただし、基本的に写真は今あるものを映すという特性があり、写した写真は写した写真以上でも以下でもない。構図の作り方や切り取り方の上手下手は当然あるが、そのものを創造したわけではなく基本的には世界からの借り物である。
芸術とは、目に見えない物を見えるようにする行為だとパウル・クレーは言っている。であれば、そもそも写真は目の前の景色をそのまま写すのであるから、芸術とはなりえないのではないか?と思ったりもしたけれど実はそうではない。作家の意図を汲み入れた写真は、その見方を大きく変えうるからだ。
作家の北 桂樹さんは、街灯を題材にポートレートを撮っている。彼の言葉を引用する。
街灯というモチーフに興味を持ち始めたのは3.11の直後にあった計画停電の時だった。
その当時夜になっても光を灯さず街に佇む街灯を見上げた時、
その個性的な姿はまるで電気の死顔を形どったデスマスクのように
私には思えてならなかった。
それ以降、この街灯というモチーフに否応なく惹かれた私は、
家族、友人、世話になった人、かつて思いを寄せた人たちなど
自身に影響を与えた私の人生のペルソナ(登場人物)たちを重ね合わせ
ポートレートとして無心に撮影していた。
今思えば大切な人たちを失うということが
どういうことなのかと考えていたのかもしれない。
彼が撮っているのは、街灯である。電気を1つの見えるカタチへと導く役割を担う鉄の棒である。僕の解釈では、彼は光を灯すことで初めてその役割を全うする街灯をメタファーとして、生きるということを表現したのではないかと思っている。光を灯さなくなった街灯は、生きることが叶わなくなった人間だということだろう。そういう観点で街灯を見上げると、大切な人の顔が浮かび上がってきそうだ。
作品づくりに必要な観点
目に見えてるはずの被写体、景色からそれ以外の「何か」を感じさせられる写真家は、やはり芸術家といえるだろうと思う。ただし、写真家にとっては写真の技術以上に重要なものがあるように思う。
彼は作品として世に出すためには審美性、社会性、時代性の観点から考える必要があると言っていたが、これとは別にも重要な視点があると思う。まず自分自身が訴えたいこと、次に訴えなければならない哲学、カタチにする想像力、そして次に表現する技術力があるのだと思う。
繰り返しになるが世の中に素晴らしい写真があふれる今の時代に、自分が敢えて撮る必要性が大事なのだ、無くてはならないのだ。
こう考えると、必ずしも巧さが重要なわけではないことがわかる。それは北さんも言っていた。自分自身が表現したいものに合った手法を選択し、作り上げるまでが作品作りの工程だと。巧さが必要であればそれを追い求めるべきだろうし、逆に拙さが必要なこともあるかもしれない。全てひっくるめて自分の作品である、自分で考えなければならない。
そして、何よりも継続する姿勢が重要である。作品の価値を担保してくれた有識者やギャラリーに加え、その価値を理解し作品を求めてくれたコレクターのためにも辞めるわけにはいかない。辞めた瞬間ゴミとなる可能性も大いにある。
死ねば価値があがるのはそれ以上作ることが不可能だから。それはいい。死んで作れない、作りたくても作れない、だから作れる状態にあるうちは作り続けなければならない。死ぬまで。自分自身の執念に呪われて初めて生涯の作家となりえるのかもしれない。