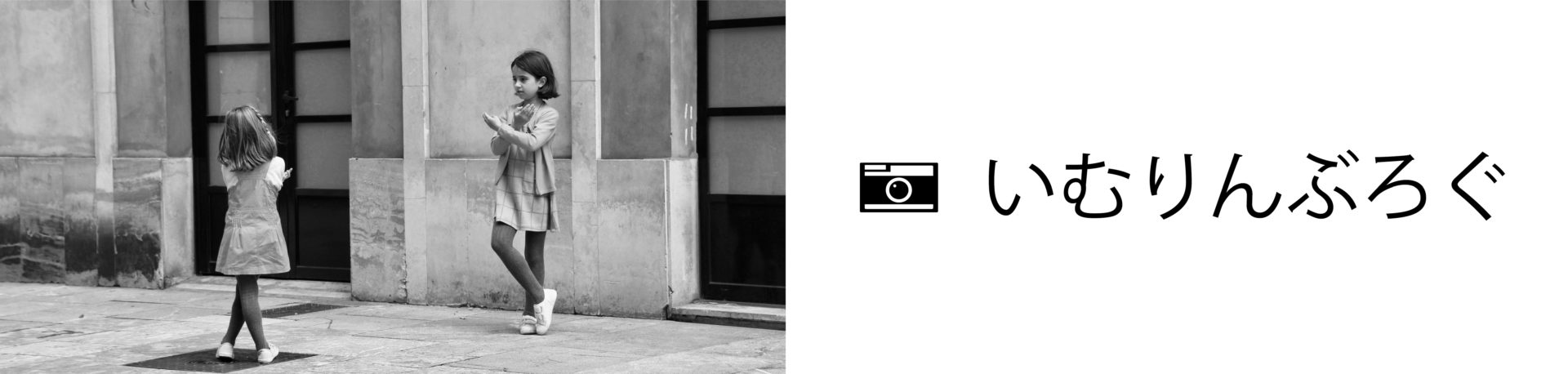先日の哲学の勉強で興味を持った一人を掘り下げてみた。バートランド・ラッセルである。こういう人を天才というのだろう、実に面白い人だった。読んだのは「ラッセル」金子光男著のもので、1968年に清水書院から出ている。
バートランド・ラッセルは、1872年5月18日イギリスの南西部ウェールズの名門貴族のラッセル家の次男として生まれた。生涯を通じて学んだ彼の思想的展開は哲学、論理学、数学に主軸を置きつつも様々な領域に広がっており、また著作の執筆だけでなく学校運営や反戦運動など自らが主体となって精力的に具体的活動を行った。そして結婚を4回も経験していて最後は80歳を超えての結婚。
彼を紹介するとしたときに、哲学者、科学者、教育者、平和主義者など1つの枠で語ることは到底出来ない。どの要素も彼であるが、一つでも欠ければ私達が知るラッセルにはならない。ただ全ての肩書を通して彼を見たとしても共通して見えるものがある、「知性と愛情」だ。
彼の愛は自分自身や家族だけに留まらず、ビーコンヒルスクールという学校を開校し、真なる人間教育を目指すために自ら教育事業も手がけている。こうした行動は彼の人類愛への挑戦の始まりの証である。彼の想いは、ついには反戦運動や原水爆禁止のスピーチといった人類全体の愛を説くまでに発展していく。肩書ではなく一人の人間として語ることで、当たり前にわかるはずの平和についてもう一度人類に問うたのだ。
科学を愛情を持って制する。愛のために科学を使わなければ、その技術はただ破滅に向かってしまう。国や民族、イデオロギーを超えてこの星に住む生命体として何を成すべきなのか、彼はその命を燃やしながら切々と訴えた。ラッセルは単なる思想家としではなく、行動で示す活動家であった。
そして彼が書いた幸福論についてもまとめてみた。読んだのは、「ラッセル幸福論」安藤貞夫訳のもので岩波文書店から出ている。
ラッセルの幸福論の特徴は、思想や精神世界の話ではなく、個人の努力次第で幸福を得ることができるという実用的な点にある。つまり技術としての幸福論である。というのも彼は掲載している内容について、全て自分自身が経験、観察したもの、つまり検証済みのものであり考えや思想だけに留まるものではないからである。また、ラッセルの幸福論は古代ギリシャのような遠い世界ではなく、現在の私達とほぼ同時代を生きている中で書かれたものであることは、いわゆる哲学書よりも入っていきやすい。時代を超えて現代社会に生きる私達にも響く内容となっている。
ラッセルは幸福になるためには幸福になる技術と同時に、不幸を遠ざける技術が求められると言っている。それ故に彼の幸福論は2部構成で作られており、1部が不幸について掘り下げ、2部で幸福について言及している。
章ごとに独立した考察が展開されるが、読み終えてみれば全ての章が関係性を持っていることがわかる。その中でも本書のキーとなるのが、16章の「努力とあきらめ」ではないだろうか。幸福を得るにしろ不幸を取り除くにしろ、全てにおいて限度やバランスが求められるとし、中庸という言葉で表現されている。この中庸という言葉自体はこの章以外には見当たらないが、表現の方法を変えて度々確認されることから、彼がこの幸福論において一貫して伝えているメッセージであると考える。
中庸の対象は、妬みや被害妄想など否定的なものに限らず、比較的よい意味で使われる言葉においても当てはまる。例えば愛情においては一方の愛情だけが強すぎてもいけないし、成功や競争においても度が過ぎることは内的、外的なバランスを崩すことにつながっていく。このバランスの崩れた量だけ自分自身にストレスを貯め、外的には被害者や敵を生み出すことになり、次なる悲劇につながっていく。そして、もとに戻すためには本来必要のないエネルギーをかけることになる。
「この世の有益な仕事の半分は、有害な仕事と闘うことから成り立っている」という言葉は現代社会でも大いに当てはまる。負のループを取り除くための中庸であると同時に、幸福を得るためには、やはり中庸というキーワードが鍵を握っているのである。「足るを知る」ことで安定した人間的な生活を送ることができる。
最後に、芸術を志す私達の観点から特徴的であった芸術家の幸福(不幸)についての記述に触れる。彼は本書の所々で一般人と比較する形で芸術家を取り上げており、中でも10章においては、幸福を追求する上で芸術家という生き物が最も遠いところにいるとの記載がある。芸術家の社会的地位は科学者などより格段に低いと彼は言う。基本的に科学者は無条件に全ての人から尊敬される立場にある一方、芸術家の持つ偉大な芸術を生み出す力は、しばしば不幸な基質と結びついていて、才能が発揮されれば軽蔑され、発揮できなければ卑屈になるという救いがたい表現がなされている。
ただし、私は本書を読み終えて、ここで彼が言う芸術家は自分自身の内面とのみ向き合っている人に対してのみであり、現代のアート事情には当てはまらないと考える。むしろ、彼が書いた14章の「仕事」、15章の「私心のない興味」このあたりを参考にすることで、ソーシャルエンゲージドアート(社会への問題提起や地域活性を絡める芸術)の領域で活躍するうえでとても参考になると考える。不幸から始まる芸術は否定しないが、一方で芸術家も幸せになれる表現手段が存在することも付け加えておきたい。
ま、この人はこんな文字量では表しきれないので、ぜひ興味を持たれたら読んでみてほしいと思います。
ラッセルの人となりを知るにはこちら
ラッセルの幸福論はこちら