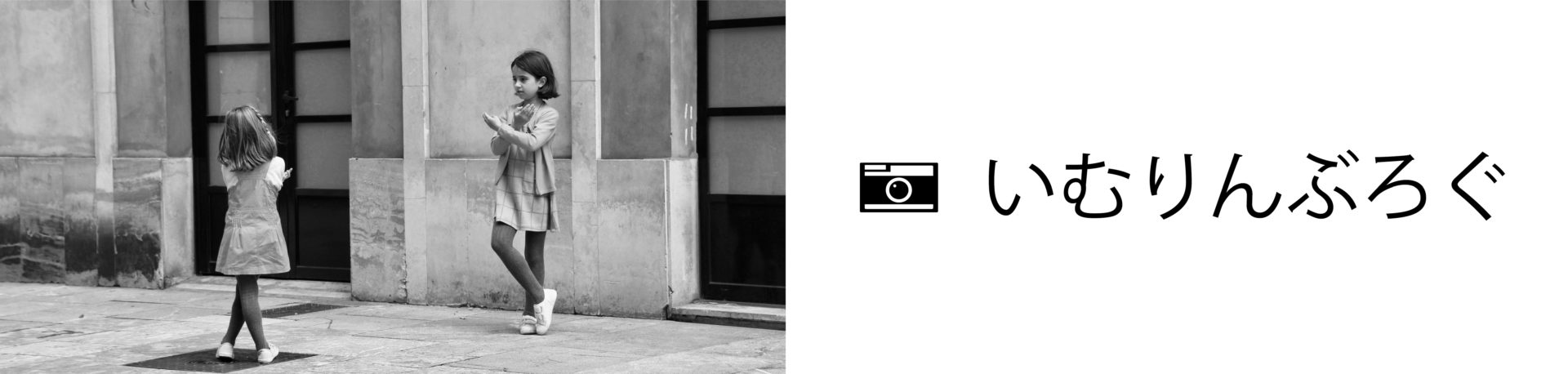こちらでは、通信にて京都芸術大学の学芸員過程で履修したレポートをアップしています。
社会人になって大学入るという人は、大人の方多いですよね。なかなか先輩のレポート見せてもらう機会ないじゃないですか。僕も一度も先輩には見せてもらえなかったので。。。しかも通信とかならなおさらですよね。ということで、これから通信で学芸員とるぞって人のために、拙いですが合格したレポート全て、全文載せておきます。
まあ自分的にも1回出して終了よりも、誰かの役に立ってもらったほうが嬉しいですし。なるほど、こんなもんかあ、とか思ってもらえる材料になればいいかなと。もちろん無断転載や転用などの著作権の侵害となるようなことはなしで、本レポートはあくまでも参考にということでお願いします。お役に立てば嬉しいです。(ちなみに地元和歌山なので、和歌山ネタレポートわりとあります。)
【博物館情報・メディア論】のシラバス記載の到達目標
学芸員過程の必修科目【博物館情報・メディア論】のレポート提出課題における、シラバス記載の到達目標は次のようなものです。そのまま引用します。
博物館における情報・メディアの活用は、コンピューター等の進展に伴う情報技術革新により、ますます重要となっています。そして、各博物館において実践される情報の管理・提供、教育普及などの博物館活動は、広く公共に還元するという点で、地域の社会教育・生涯学習に重要な役割を担うものといえます。本科目では、博物館における情報・メディアの理論について、その活用方法、情報発信、知的財産などの観点から学習します。
2つ以上の異なる博物館を採り上げ、それぞれ、どのような情報・メディアが活用されているか、博物館活動の情報化の観点から、具体的事例をあげ、比較して論じなさい(3,200字程度)。 ※必要に応じて画像や資料なども添付し、参照した参考文献、資料、URL(参照年月日を明記)等は、注などを用いて必ず書誌情報を明記すること。 ※レポート全体の趣旨を表すタイトルを文頭に記すこと。
京都芸術大学(旧京都造形芸術大学)シラバス2021から引用
ここからが提出したレポートです。
【博物館資料保存論】レポート:「資料の活用が保存を促進させる社会における循環形成」「3つの美術館から見る情報の取り扱いと問題点」
はじめに
博物館活動の情報化を論じるうえで美術館に絞って調査を進めた。地域性の観点から渋谷区立松濤美術館、客層の幅や規模の大きさの観点から国立西洋美術館、作家が存命かつ取り扱いが特殊な現代アートという観点からワタリウム 美術館を選定した。テキスト内の情報の種類、伝達手段を参考に分類を作成し美術館ごとの特徴を整理したうえで、問題点と改善案を述べる。
■資料コレクション・展覧会・調査研究に関する情報
・松濤美術館
渋谷にゆかりのある作家のコレクションや区内に在住するコレクターの作品の展示、現役作家の特別陳列が行われるほか、渋谷区小中学生絵画展も行われている。
・西洋美術館
日本の美術館としてトップレベルの認知度を誇る館であり、松方コレクションを基礎とした西洋の美術作品を専門とし活動している。国内外問わず観光客が多く、展示の作品リストや説明パネル、HPなどは英語、中国語、韓国語にも対応している。
組織図や担当者名などもHPにて公開されている。
・ワタリウム 美術館
現代アートを中心に活動を行う。作家が存命なことも多く、展示プランには学芸員のほか作家の意思が含まれており、インスタレーション形式の展示も多く見られる。
■データベースに関する情報
・松濤美術館
所蔵作品については、現在HPは準備段階であり簡易リストのみリンクが貼られている。
・西洋美術館
所蔵作品は、作家名、作品名のどちらからも検索可能。分類が細かく写真付き、作品解説もあり検索者の使い勝手は良い。またGoogle Arts & Cultureで、自宅から作品とその解説が見ることができる。併設の国立西洋美術館研究資料センターでは、関係職員や大学院生限定で研究資料の閲覧が可能である。
・ワタリウム 美術館
所蔵作品はHPに掲載されており、ARTIST、PHOTOGRAPHERの二つに分けられている。情報は氏名と出身国程度である。なおコレクション掲載ページはトップページからは行けず、わかりづらい構造である。
■建築設備・管理運営評価に関する情報
・松濤美術館
白井晟一設計で、建物の評判も良い。設立前は公会堂や総合体育館などの他の文化施設の建設企画もあったが高級住宅街という土地情報を鑑み美術館に決定した背景がある。美術館という存在自体が地域性を表すメッセージとして機能している。館内には木彫りの案内板など建物に合わせた表示が確認できる。
HPには美術館年報や30周年誌などの出版物もアップされており、活動記録や入館状況などは随時確認することができる。
・西洋美術館
設計はル・コルビュジエが手がけ、建物が世界文化遺産に認定されており、建築仕様を解説する音声ガイドも用意されている。また館内MAPはHPに掲載されている。
館の実績報告書等の評価情報は外部サイト(独立行政法人 国立美術館)で公開されている。
・ワタリウム 美術館
マリオ・ボッタが手がけ建物にアートの先端としてのイメージが内包されている。内部は吹き抜け構造で、インスタレーション形式の展示などでは空間も意識して観覧することが好ましく、得られる情報量、解釈の幅は広い。
■各種教育普及事業・人的手段に関する情報
・松濤美術館
展示以外の活動では講演会やギャラリートークに加え、ワークショップや美術教室、映画上映やコンサートなど幅広い。美術館内部の建築ツアーも定期的に開催されている。
・西洋美術館
教育普及情報はHPで随時更新されており、ギャラリートークやワークショップ、講演会に建築ツアーとラインナップは幅広い。毎年「美術館でクリスマス」というコンサート、ペーパークラフトなど独自性のある伝達手段が用意されている。
研究報告は講演会と交えて行われており、直近では2019年12月にシンポジウム「ピカソとバルセロナ」がある。
・ワタリウム 美術館
教育普及コンテンツの過去実績は多岐に渡り、著名なキュレーターをゲスト講師として呼ぶ講演会や、アートを基盤に幼児教育について考える「子どもたちの未来研究会」がある。しかし現在のイベント実施数は減少傾向にある。
■広報関係(ウェブサイト・SNS・マスコミ)・刊行物、図録に関する情報
・松濤美術館
活用SNSはツイッター、フェイスブック、インスタグラムで、展示情報やイベント情報が更新されている。また学芸員の寄稿なども各種美術メディアにて確認できる。HPでは館長ブログ「館長室の窓から」にて、過去の展示報告や今後も展示の見どころなどの情報が更新されている。ミュージアムショップは常設されておらず、オンラインで図録などが購入できる。
・西洋美術館
活用SNSはツイッター、フェイスブックで、館の運営情報や実施イベント情報が配信されている。HPの更新頻度も高く、メディア掲載情報のほか新たな作品購入情報についても更新される。
寄付の募集ページからは国立美術館のオンライン寄付サイトに遷移し、資金をどのように使用するのかなどの情報も得ることができる。
出版物には所蔵作品の図録や展示カタログがあり、HPでは美術館概要や研究紀要、広報誌を閲覧できる。
・ワタリウム 美術館
活用SNSはツイッターやインスタグラムに加えて本人インタビューなどを掲載できるvimeo(動画共有サービス)がある。館以外のメディアでも特集されることがあるため、HPへのリンクや、会場内で閲覧できるようになっている。
出版や刊行物については、実施する展覧会のカタログや図録のほか、制作風景やパフォーマンスを解説する映像を作成している。
「夢みる美術館計画 ワタリウム美術館の仕事術」という書籍も日東書院より出版されており、美術館の仕事紹介がされている。
ミュージアムショップでは過去の展示カタログやポストカードも販売されており、オンラインショップも用意されている。
■3つの館を踏まえた考察
松濤美術館のような地域の美術館は動員人数は限られるため、展示は見えやすい。しかし存続のためには動員数の増加は重要である。そのためには展示情報の充実はもちろんだが、地域住民との関係性を強化する広報的な情報拡散に力を入れる必要はある。
一方で、西洋美術館のように来館数が多い美術館は作品の個々の解説パネルなどが見えづらくなる。例えば情報端末の貸し出しや、アプリなどを用意して鑑賞者の手元で情報が確認できるような仕組みは必要だと考える。外国人客も理解しやすくなり国別の印刷なども不要になるメリットもある。
またその他の美術館では稀だが、ワタリウム 美術館は鑑賞者が自由に写真を撮って良い展示が多い。作品自体の著作権については用途を守れば担保されるが、権利問題を詳しく知る鑑賞者は限られるため、鑑賞者同士の写り込みによる写真の活用や肖像権については一定の注意が必要となる。
イベント参加の際の個人情報の取り扱いについても、注意が必要である。私自身ワタリウム美術館主催の「大拙を体験する2020」という教育普及イベントに申し込んだ際、専用フォームはなくメールに個人情報を打ち込む形式であり、また受付完了の返信も時差があるなど個人情報取得、保管の観点においては管理体制は再考の余地がありそうであった。
参考文献
- 今村信隆編、「博物館の歴史・理論・実践2 博物館という問い」、藝術学舎、2017年
- 全国大学博物館学講座協議会西日本部会編、「新時代の博物館学」、芙蓉書房出版、2015年
- 松濤美術館
- 松濤美術館オンラインストア
- 松濤美術館ツイッター
- 松濤美術館フェイスブック
- 松濤美術館インスタグラム
- 国立西洋美術館
- 国立西洋美術館研究資料センター
- 国立西洋美術館 Google Arts & Culture
- 独立行政法人 国立美術館
- 国立西洋美術館フェイスブック
- 国立西洋美術館ツイッター
- ワタリウム美術館
- ワタリウム 美術館オンラインショップ
- ワタリウム美術館ツイッター
- ワタリウム美術館インスタグラム
- ワタリウム美術館vimeo
今回参考にした書籍です。レポート書くにあたっては複数の書籍を読んだ方が、重要なポイントの理解、解釈の広がりが見えて良いと思います。ネタに使える引き出しも増えますしおすすめです。