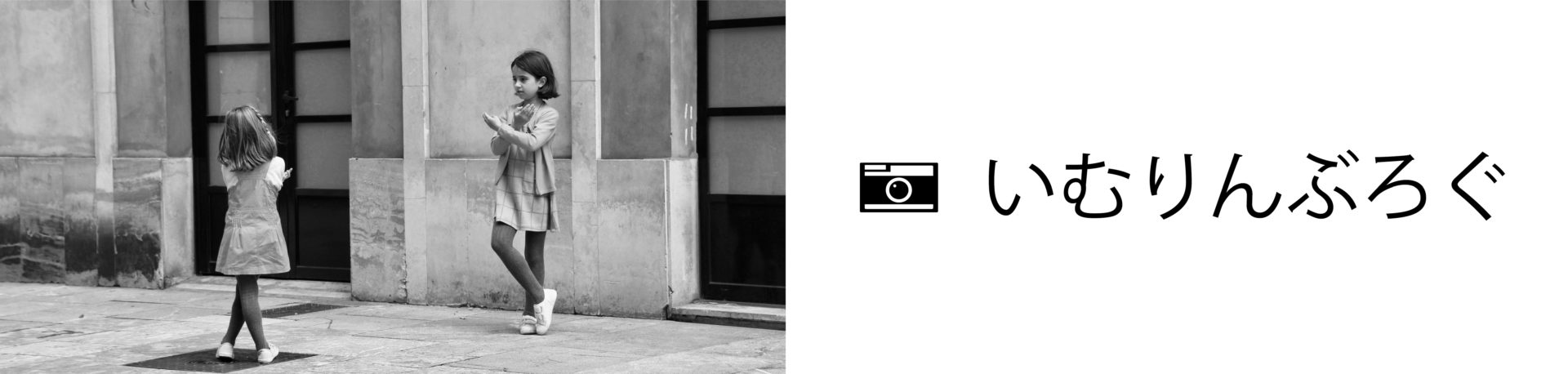1人の写真家を掘り下げるという機会があった。写真家の中でも特に僕が注目しているのが、深瀬昌久だ。いろんなページを参考にして、彼について掘り下げを行なってみた。参考にしたページの紹介や、その解釈、そして自分自身が深瀬に感じたことをまとめている。
内容をせっかくなので、アップしておこうと思う。散りばめた写真は彼を意識して撮影したもので、その模倣作品に関するコメントは後半にまとめて記載しています。
写真家の氏名 と生誕年
深瀬 昌久(ふかせ まさひさ、本名よしひさ)
1934年2月25日 – 2012年6月9日
作家の概要や経歴
深瀬昌久は「自分とは何か」を追求し続けた写真家として知られ、モチーフは家族、カラス、猫などがあげられる。また最終的には水中カメラを使って自分自身を取り続ける今で言うセルフィーとも言える作品を残している。
このように身近なものを題材に据えているが、モチーフの変遷の中で徐々にそして確実に自分自身へと向き合おうとシャッターを切っているように伺える。(自身の飼い猫を撮るにしても「猫の瞳に自分を映した自写像である」と表現し、また「カメラ毎日」での『烏』連載においても、制作のきっかけとなった76年の北海道への旅を綴った手記の中で「カメラを持った烏になって、黒い友達を追って遊んでいた」と綴っている。)
特に代表的な作品の被写体である鴉は、彼が感じていたであろう実存的な苦悩と寂寥を反映したものであるというだけでなく、鴉に自身を重ね合わせることを通して、狂気に満ちた芸術的表現へと昇華させたという見方がある。
深瀬は、「いつも愛する者を、写真を写すという名目で巻き添えにし、自分も含めて誰も幸せにできなかった。写真を撮るのは楽しいか?」と自らの過去を振り返ると共に、「すべてをやめたいと思いつつ写真するぼくの作業は、いま生きていることへの復讐劇かもしれない」という言葉を遺しているとおり、写真を愛し、そして写真に殺された孤独な表現者であった。
1992年、深瀬は行きつけのバーの階段から転落する。個展「私景シリーズ92’」開催直後の6月20日深夜、新宿ゴールデン街にある「南海」の階段から泥酔して転落、脳挫傷のため重度の障害を負う。以降、二度とカメラを手にすることはできなくなった。2012年 – 6月9日、脳出血で死去。78年の生涯に幕をおろした。

以下ウィキペデイアより
略歴
- 1934年 – 2月25日、深瀬写真館の二代目である父・深瀬助造、母・みつゑの長男として生まれる。
- 1946年 – 北海道立名寄中学校に入学。
- 1949年 – 北海道名寄高等学校に入学。
- 1952年 – 日本大学芸術学部写真学科に入学。
- 1956年 – 第一宣伝社に入社、広告写真を撮る。
- 1960年 – 初の個展を開催。『コマーシャルフォト』の編集者であった玉田顕一郎の目にとまり、写真評論家・吉村伸哉を紹介される。
- 1961年 – 個展「豚を殺せ!」を開催。
- 1963年 – 「朝がくる」を『カメラ毎日』に発表。
- 1964年 – 日本大学の1年後輩の高梨豊に誘われ、日本デザインセンターに転職。鰐部洋子と結婚。
- 1967年 – 河出書房写真部長に就任。
- 1968年 – 河出書房が倒産、退社しフリーランスとなる。
- 1971年 – 写真集『遊戯』刊行。
- 1974年 – 荒木経惟、東松照明、細江英公、横須賀功光、森山大道とともに「ワークショップ写真学校」を開講(-1976年)。
- 1974年 – ニューヨーク近代美術館「NJP展」、東京国立近代美術館「15人の写真家展」に参加。
- 1976年 – 洋子と離婚。石川佳世子と再婚。
- 1987年 – 1月、父・助造死去、享年74。
- 1989年 – 深瀬写真館が廃業となる。
- 1992年 – 石川佳世子と離婚。個展「私景シリーズ92’」開催直後の6月20日深夜、新宿ゴールデン街にある「南海」の階段から泥酔して転落、脳挫傷のため重度の障害を負う。以降、二度とカメラを手にすることはできなくなった。
- 2012年 – 6月9日、脳出血で死去。78歳没[1]。
写真集
- 『遊戯』中央公論社、1971年
- 『洋子』朝日ソノラマ、1978年
- 『ビバ! サスケ』ペットライフ社、1978年
- 『サスケ、いとしき猫よ』青年書館、1979年
- 『猫の麦わら帽子』文化出版局、1979年
- 『空海と高野山』1982年
- 『Black Sun:The Eyes of Four』Aperture、1986年(共著)
- 『鴉』蒼穹舎、1986年12月15日
- 『父の記憶』IPC、1991年
- 『家族』IPC、1991年
- 『The Solitude of Ravens』Bedford Arts、1991年6月(『鴉』英語版)
- 『日本の写真家34 深瀬昌久』岩波書店、1998年
- 『bukubuku』hysteric glamour、2004年
- 『hysteric twelve 歩く眼』hysteric glamour、2004年
- 『鴉 Solitude of Ravens』RAT HOLE、2008年
- 『屠 Slaughter』SUPER LABO、2015年
- 『Wonderful Days』roshin books、2015年
- 『Hibi』Mack、2016年

写真集や代表作など
代表作「鴉」について
代表作の『鴉』は、深瀬が妻との別離を起因とした悲しみに暮れながら故郷に向かった旅を出発点とし、1976年から1986年にかけて撮影された。北海道の海岸沿いの景色を背景に旅の途上で出会った人やものを写した作品である。写真集は寂寥の気配を漂わせる鴉の群れをの他、女子高生のなびく髪や女性の裸体など、一言では言い表せないような含みをもたせた写真が収録されている。1986年に初版が刊行され、その後、2度復刻されているが、いずれも限定部数での発行だったこともあり、直ちに完売となっている。

「烏」と「鴉」
「鴉」という漢字が写真集に使われていることは周知の事実であるが、一方で雑誌と展示では「烏」と題されていた。それについて深瀬は『カメラ毎日』にこう記していいる。“烏”という字は象形文字で、カラスは真っ黒で目が見えないから「鳥」の目の位置に当たる一本の線を抜いて「烏」とした。一方の「鴉」は形声で、「牙」(ガ)の音がカラスのカーという鳴き声を表す文字であると。1976年の一回目の展示で悩んだ末、形声より象形を選んで「烏」にした。当初は、カラスの形態にフォーカスを当てていたことが伺える。
「CROW」ではなく「RAVEN」
カラスは英語で「CROW」と「RAVEN」があるが、深瀬の写真集では「RAVEN」とされている。「CROW」は体が小さく都会に住みやすいハシブトカラスやハシボソカラスのことで、日本では古来から「八咫烏」信仰に見られるような吉兆を示す鳥ですが、対する「RAVEN」は大型のワタリガラスを指し、これは不吉の兆しを持つ鳥として海外のさまざまな神話に登場している。当時70年台に翻訳されたエドガー・アラン・ポーによる有名な詩『大鴉』の原題が「RAVEN」で、当時の幻想文学好きに好まれていたことも関係しているとも考えられている。
物語の中で、ある嵐の夜に、恋人を亡くした男性のもとに言葉をしゃべる鴉が突然現れ、男性が鴉に「お前は何者なんだ」「自分の失った恋人をお前は返してくれるのか」などと問う。鴉は「Never more(二度とない)」とだけ返すという残酷な詩である。
恋人を失う過程で鴉が出てくるという構造は、当時の深瀬の状況、そして深瀬の二冊目の写真集『洋子』にも繋がりが見いだすことができる。深瀬と当時の妻は1963年に出会って翌年には結婚するが、度重なる衝突を経て深瀬は二度の家出をしたのち、ある日ふらっと舞い戻る。しかしそれは妻を一年間撮るためであり、76年には離婚をしてしまいます。この写真群が78年に写真集『洋子』として出版。『鴉』はその次に出版されている。
「洋子」と「鴉」
『洋子』が出版される前、深瀬は妻の故郷である金沢を訪れ、木々から飛び立つ数多のカラスを撮影している。その時の写真は『鴉』だけでなく、『洋子』のラストに配置されている。まるで『大鴉』に登場した鴉が男の前から飛び去るシーンを実際に描いたかのようにも見える。
深瀬の『鴉』を考えるうえで前作『洋子』は欠かせない作品なんです。後に『鴉』の中に収められる印象的な写真が、このときすでに撮られている。『鴉』と『洋子』は2つで1つの作品であるという見方が出来るのではないか。

作家を読み解くキーワード
彼を語る上でキーワードとなるものもまとめた。何だこれ?と思われるものもあるかもしれないが、これは随分と解釈が入っているので、あくまでも公式的なもの(そんなものあるのか?)ではなく個人的な見解です。
洋子・鴉・ブクブク・石川・北海道・自分・闇・孤独・エゴイスト・悲しみ・好奇心・底・一体・セルフィー・猫・サスケ・黒・葛藤・モノクロ・カラー・モンタージュ・狂気・タバコ・酒・ゴールデン街・新宿・暇つぶし・子供・人間・興味・不器用・不気味

作家や作品について
深瀬は文字通り写真に取り憑かれていた。愛妻であった洋子への気持ちがあったことは彼の写真集「洋子」を見れば一目瞭然である。だが男と女よりも写真家と被写体という関係性を彼は選択肢した(させられた)のだ。時にはかけたい言葉を飲み込みファインダーを覗き、触れる代わりに静かにシャッターをきったことだろう。彼は写真作品による被害者だった。
写真は被写体を撮るものなのか、それとも被写体に撮らされるものなのか。深瀬は写真家と被写体の関係性、そしてカメラという媒介について考えさせる作家である。

模倣写真の制作意図
STEP1 「自分とは何者か?」
彼の作品を通して、考えることは先述(「写真は被写体を撮るものなのか、それとも被写体に撮らされるものなのか。彼の作品を通して、その間に存在するカメラという媒体を考えさせられる。」)のとおりだ。彼の作品を通して、私が最も印象に残っている被写体は、代表的な「鴉」の中のカラス、盲目のマッサージ師、魚、そして「屠」の中の異様なメイクを施した妻洋子である。
「自分とは何者か?」この問のために写真を撮ったのが深瀬だというレビューをよく見かける。彼はカラスに自分自身を投影していたと言うような表現は至る所で見つけることが出来るし、妻洋子の言葉においてもこのような言葉が残されている。「彼の写した私は、まごうことない彼自身でしかなかった」そして、最終的には風呂場で自分自身を写した「ブクブク」という作品である、彼の作品は全てがセルフポートレートだったとも言えるかもしれない。
私は彼の構図やモチーフを模倣することはもちろんだが、その想いこそ模倣すべき対象であると考えた。つまり「自分とは何者なのか?」これを見つけるための写真であるべきなのだ。私が映る被写体とはいったい何であるのか?目の前の被写体を通して私というものを考える行為を行なった。

STEP2「人間が住まう世界とは何なのか?」
また「自分とは何か?」という問を本質的に考えるに当たっては、そのベースとなる「人間が住まう世界とは何なのか?」という問に触れずには進むことはできないのではないか。
着実に歴史を積み重ねてきた科学的な世界と見る一方で、人間以外が存在する自然界の文脈とは圧倒的に異なる世界でもある。自然の摂理ではなく、人工的な仕組み(妄想や空想)の上に成り立つ虚構としての世界という一面だ。
そのような目線で見たときに、この世界はとても危ういのではないかと思う。(国家が破綻し、通貨が紙切れになる等もこれに当たる)私は嘘を誠にしたような危うい世界に住まう我々を考える上で、リアルの世界にフェイクともとれる存在(「屠」の中の洋子)を配置することを考えた。
現実世界の人間に表情を奪う化粧を施す。この世には存在しない不確かな存在を配置することで、いつもの景色に違和感は生まれはしないだろうか。作り物のように見えはしないだろうか。そう考えると、世界があるから人がいるのではなく、人がいるからこそ世界は成り立つと考えられる。これは自然の中に生物が住む自然界とは真逆の考えだ。
私たちは一体何であるのか、そして私達が住む世界とは何であるのか。不確かな存在の撮影を通して、自分や自分が今在る世界を問うことを目的に撮影した。


アラーキーと深瀬昌久のセルフポートレートも比較してみた
以上が今回僕が深瀬昌久を掘り下げたもの、見る人によって感じ方が異なるのが写真である。当然私が感じる深瀬と誰かが感じる深瀬は異なるだろう。でもそうした異なる意見を知ることで、自分自身の見方もまた変化する。そうして多角的に作品を鑑賞する大切さを近頃痛感している。
まだまだ拙い観察であることは自覚はしているものの、これを見ていただいた方に、そのようなスパイスの1つになってもらえたら嬉しい。
あわせてアラーキーと深瀬昌久のセルフポートレートを比較したものも書いていますので、興味があればぜひ御覧いただければと思います。
この記事を書くにあたってはいろんな文献参考にしましたが、写真集も見ました。今買うならこちらがおすすめですね。かなりごっついです。図鑑です。うちにもありますが、泥棒きたらこれで応戦できそうなほどの重量の情報量が詰まっています。深瀬好きの方はぜひ見たほうが良いと思います、おすすめです。