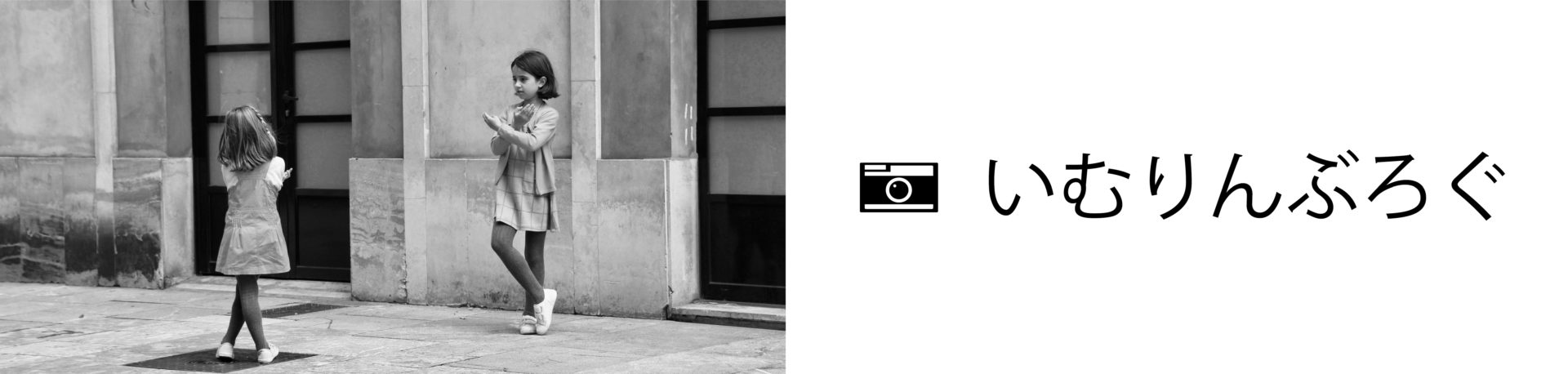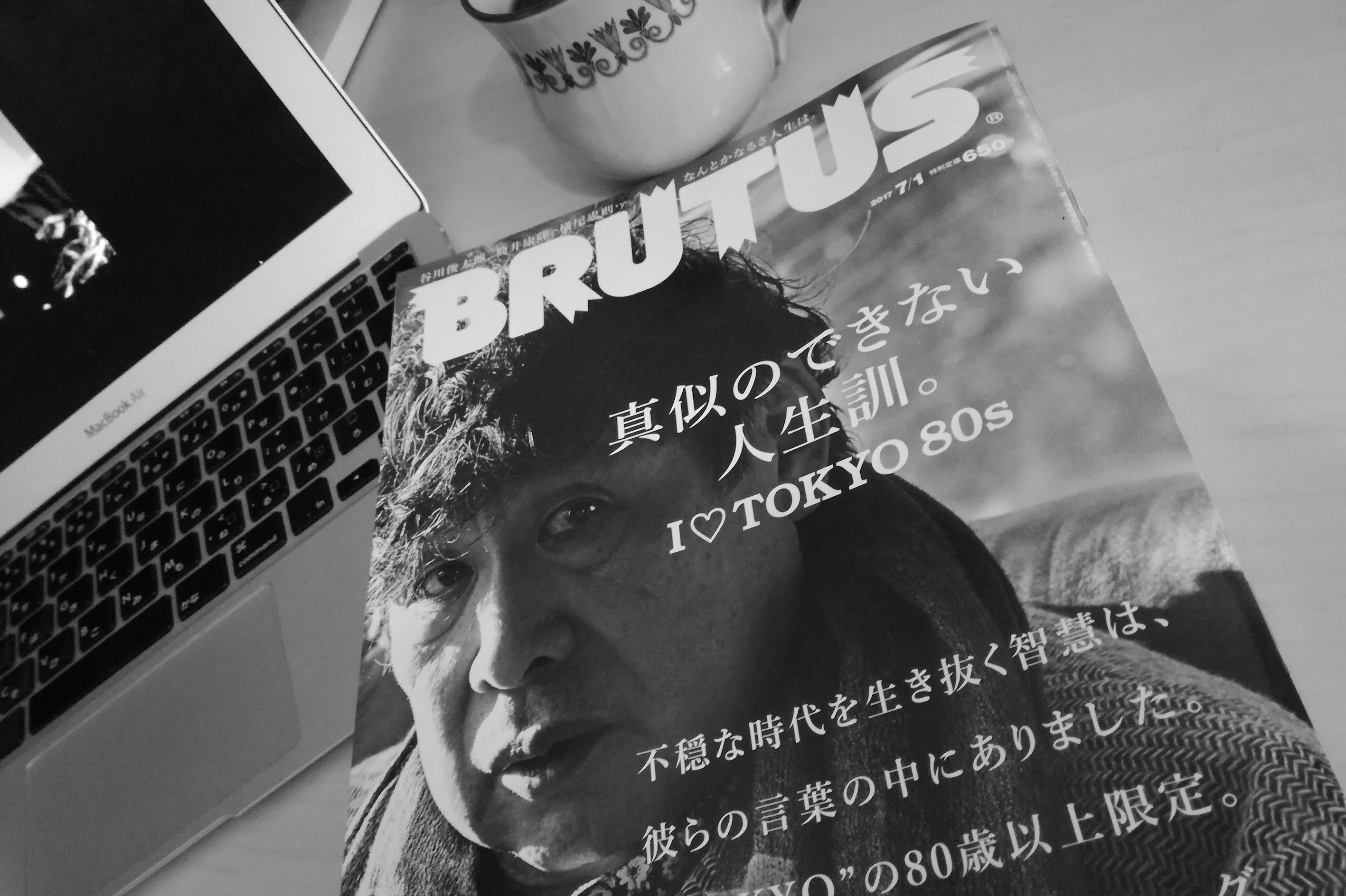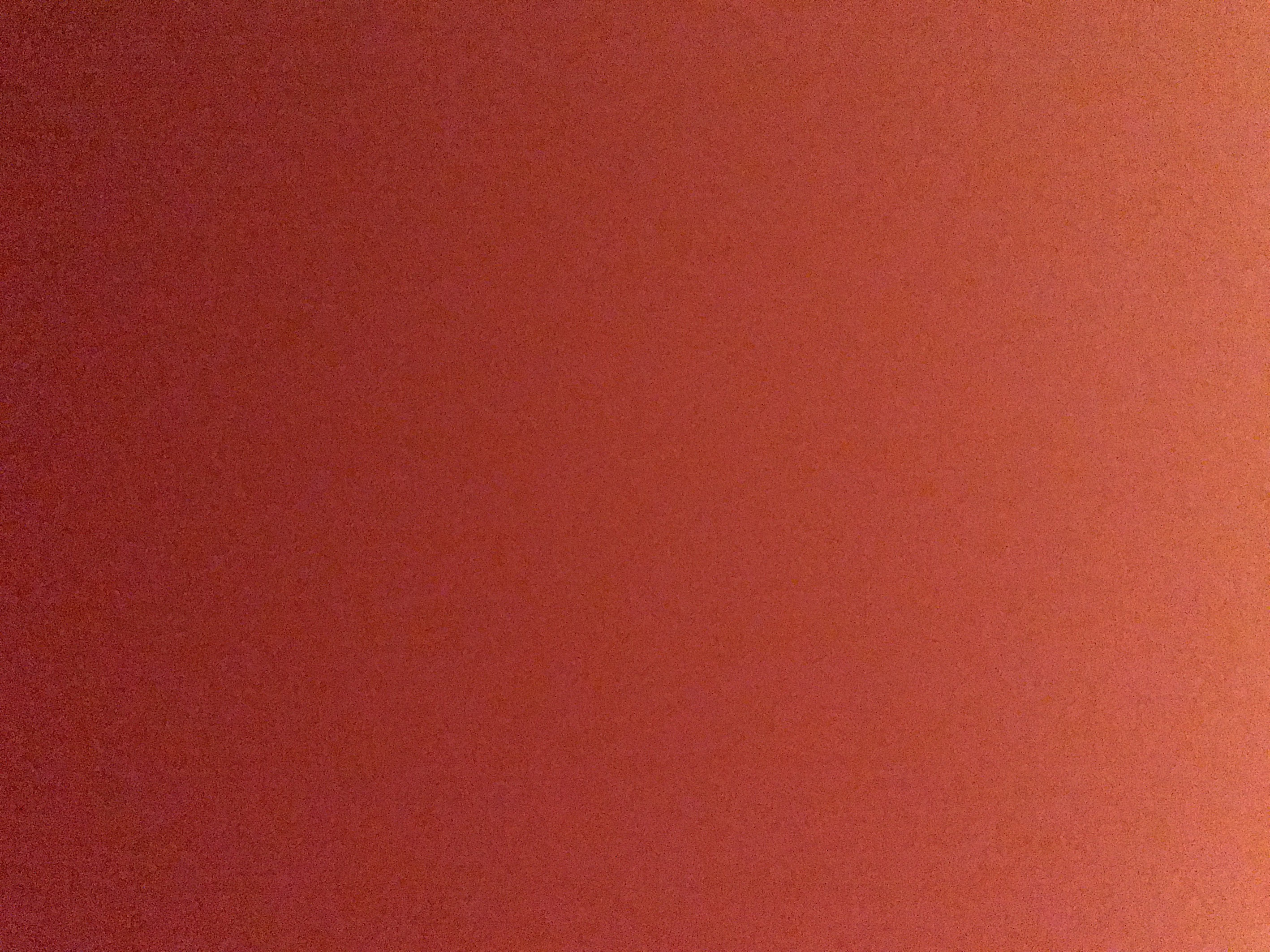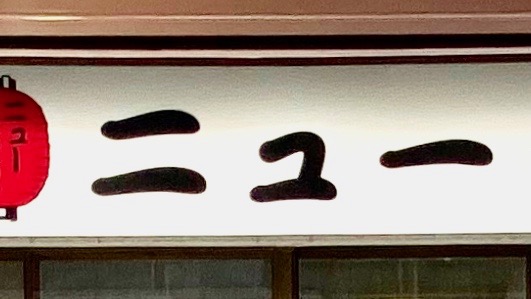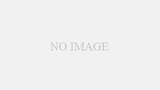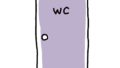こんにちはいむりんです。このページでは、現在社会人で通信制の芸大に4年通っている僕が、同じく社会人をされてる方で「芸大に入ってみようかな」と考えている人に向けて、
- 「どんなタイプの人が入学してそうなのか?」
- 「ぶっちゃけ費用はどれくらい必要なのか?」
- 「どんなことを学ぶのか?」
- 「仕事と学校生活が両立できるのか?」
などなど気になりそうなことを僕自身の経験から綴っています。また、いくつか実際の授業や課題、レポートも公開するなどリアルな情報提供を心がけて書いてみましたので、ぜひ参考にされてみてください。
社会人で芸大に入るメリット
社会人で芸大に入学してよかったことは、結構たくさんあります。
現在社会人で芸大生やってる自分と、もし自分が現役の頃に芸大に入っていたことを想像して比較したりするのですが、もしかしたら社会人になってから入学してよかったのかも?と思うことがあります。
自分の人生のこれまでが作品作りのテーマにつながる
もちろん、比較することはできないのですけど、社会人としての経験やこれまでの人生経験を経て入ることは芸術、アートに関わるという意味では非常に大きな糧になります。
具体的には、問題意識や主張したいことなど、経験を積んで表出するものですね。これは人生経験の長い社会人だからこそというポイントかなと思います。
大学で体系的に学べる
大学ですので、根本的な部分から体系的に学べることも大きいですね。趣味や独学でのネットで検索して、ツギハギで知ることとは違いますね。これは社会人だからと言うことではなく、大学という機関だからこそのメリットですね。
特に芸術系は流れや歴史が重要ですので、体系化した情報はありがたかったです。
仕事以外にコミュニティができる
また仕事以外にも別のコミュニティができること、年齢にとらわれない同期を得ることは社会人だからこそありがたく感じます。いわゆる学友というやつです。
年齢も住んでいる場所も職業もバラバラ。これはかなり面白いですし、普通に仕事の相談とかする場合もありますし、卒業した人とも飲み友だったりしますし。
学問が知識の幅を広げるのは当然ですが、交友関係も広がるのはいいことですよね。大人の学びはいいこと多いです。

社会人芸大生の実態
僕は社会人芸大生としてやってきて4年です。その中で感じた社会人芸大生の実態を記していきます。
社会人芸大生ってどんな人が多いのか?なろうとする人のタイプ
どんな人が社会人で芸大生になるのか?同期や先輩をみて思うことを紹介しておこうと思います。ちなみに僕が在籍する京都芸術大学では、東京キャンパスと京都キャンパスがあります。
ざっくりとですが僕の入学年度は東京と京都で人数は半々くらいでした。(特に決まったキャンパスに通うということはないですが、通いやすさからある程度定着します)ちなみに僕らが入学した年は2017年度ですが東京50人、京都50人って感じでした。
入学している方のタイプの詳細はこちらの記事にアップしています。
続ける(卒業する)人もいれば辞めてしまう人も
芸大って想像もつかないという人多いと思います。みんなそんな感じで入学してきます。僕もそうでした。
ただ最初は不安があっても、楽しみながら成長していく人が結構多いですね。素人スタートで作家活動を始めてしまう人もいます。まさに好きこそものの上手なれです。
また本業の仕事に活かすようになる人もいますし、ライフワークになる人もいます。そういう人が周りにいるだけでいい刺激をもらえます。
一方で、残念ながら辞めてしまう人もいるのも事実。社会人で忙しい中決心をして、芸大に入学したんだけども、早々に辞めてしまう。それぞれの事情もあるでしょうし、向き不向きも当然あるかもしれません。でも辞めてしまう方も何通りかのタイプに分かれそうな気がしています。
 僕が所属する京都芸術大学通信教育部写真コースでの所感ですけど、こちらの記事にアップしていますのでぜひご参考までに。
僕が所属する京都芸術大学通信教育部写真コースでの所感ですけど、こちらの記事にアップしていますのでぜひご参考までに。
もちろん辞めたからといって縁が切れてしまうわけではなく、僕は辞めた人とも今でも繋がっている人もいます。
ぶっちゃけ社会人の芸大生(通信制)の卒業までの費用
芸大って当たり前ですけど、大学ですからね。それなりにお金かかります。しかも「芸」大ですし作品を作るとなると、やはりお金はかかります。実際いくら学費使っていたのか、このタイミングで自分でも振り返ってみました。(今まで見ないふりしていた)
なかなかしびれる費用学費に払ってたんですね。。。でもその分得たものも大きいので、納得はしています。
学費だけ見ると、「わああああ」となるかもですけど、コロナ始まって以降、お金の使い方(僕は)変わりましたし、学費として使う分には逆にありなのでは?と思ったりもしています。
ということで、振り返った具体的な学費明細を公開しました笑
卒業した先輩や同期は作家として活躍してる人も多数
通信制の芸大での学び方
僕も入学まではアート経験はありませんでしたが、入ってみたらなんとかなります。
授業の中でおすすめの書籍や作家を教えてもらえるので、そのつながりを広げていけば知識は自然と広がっていきます。
大事なのはその方向への興味、好奇心ですね。それさえあれば後は自然とついてくるという感じです。
僕も京都芸術大学の写真コースに行き始めてから興味を持った領域(写真だけではなく本当にいろんな領域です)はたくさんあります。このブログでも公開していますので、その中から印象的だったものを公開しようと思います。

写真コースの面白かった授業の感想や気づきをまとめた記事
僕が今、京都芸術大学で専攻してるのは「写真」なので、授業や課題も写真や映像に関するものがメインです。でも「写真とは・・・?」みたいなことを掘り下げるようになってしまって、哲学とか言語学とかetcいろんなものに触手を伸ばすようになりました。
タイポロジー作品制作の課題
タイポロジーという形態で作品を作ったときの記事です。体裁はゆるいですが、わりと考えて作ったものです。
ライティングの授業
光で写真って結構変わるのですよね。むしろ写真は光を切りとる装置なので当たり前なのだけど、なかなか面白い。授業を受けて書いた記事です。
写真家を考察する課題
自分の好きな、気になる写真家を考察した課題です。実はこれで学校の事務局と揉めました。(学校に提出前にブログにアップしてしまったことで、、、)
写真というテーマを扱うことでふと思ったこと
技術だけでなく歴史を勉強することで学びに奥行き得られます。疑問が自然と湧いてきます。
映像の歴史の授業
映画好きだったのでこういうのは学びなのか娯楽だったのかという感じでした笑でもめちゃ真剣に受けてました。好きなものが授業で体系的に学べるのは大人の贅沢な学びだといえますね。
学芸員の資格課程科目のレポートと実習
社会人からの芸大編入して、うっかり学芸員課程に進んでしまったので、苦労して書いたレポートも参考に公開しようと思います。(学芸員課程は全て単位を取り終えました!後は卒業するのみ)
ますます大人の学びが大事になってくると言われてますし、家で本を読むのはもちろんいいことですけど、外に学ぶ場所を作るのもいいですよ。そして意外とアートって社会と繋がりが大きいんですよね。というか社会活動と切っても切れないというか。
こういう学びは作家を研究したり、自身が作品を作る際に考えたりしますが、学芸員過程で学ぶ中でも非常に多くを知ることができます。美術館、博物館を通して社会とアートを俯瞰して見るような感じでした。

学芸員資格取得に必要な主要8科目と関連科目
ということで、学芸員課程のカリキュラムの中のレポート、メインどころをまとめて公開しています。
学芸員過程科目の課題
学芸員課程の選択科目のレポートの1つを、リライトしてみたものです。普通にブログの記事になるような課題もあるので、やっていて楽しかったです。
その他の美術館&ギャラリー&アートイベントに関する記事
学芸員課程に入って、美術館や博物館に足を運ぶ回数が増えましたので、せっかくなのでそのあたりも。。。
京都芸術大学の学芸員実習の内容と参加した感想まとめ
通信制の大学で起こりうる単位取得に関する致命的なミス
僕は毎年単位取得関係で何かしらやらかしてます。でも、そのミスって実際誰でもあり得るので、こんなことには注意したほうがいいですということを最後にあげておきたいと思います。
こういうミス起こりがちなんですよね通信って。日頃校舎で顔を合わすとかないので、声掛けとかないじゃないですか?他の人よくやれてるなあと思いますよね笑 入学した暁にはぜひ気をつけて。。。
必修科目取得忘れによる卒業制作ストップ
今年の2021年4月からついに集大成である卒業制作に入ったんですが、必修科目の履修忘れという衝撃的な出来事があって、卒業制作が継続できないということになりました。
なので自動的に卒業できないことが確定してしまいました。悲しい。来年再リベンジです。学費。。。
まさかの剽窃疑惑をかけられ不合格判定
また先程少し触れましたが、ある科目の課題を作成したのですが、課題を学校に提出する前に自分のブログでアップしてしまいまして、その記事を見つけた学校側が剽窃判定を下して、その単位は不合格になってしまいました。
自分が作成して、自分のブログにアップしているのだから剽窃もクソもないのでは?(実際はちゃんとした書面で抗議しましたが)と食い下がりましたが、結果取り繕ってももらえませんでした。これに関しては未だに根に持っています。笑
カートシステムに入れっぱなしで授業がとれていなかった
通信制でも対面授業がいくつかあります。京都芸術大学ではそういう授業は、楽天やアマゾンのようなカートシステムがあり、授業をカートに入れて決済するという段取りがあります。(対面授業は人数が限られること、また1つの授業ごとに別途学費が発生するのです)
で、どうやらそのカートシステムにある授業を入れたはいいが、きちんと決済できていなかったようなのです。それを知らずに当日学校に行きましたら、出欠の際に名前を呼ばれない。そこで初めて授業がとれていなかったことに気がついたんです。
対面授業は基本的には年1回という仕様なので、また来年ということになってしまいました。

卒業制作終了!6年間かけて大学卒業ということになりました
2023年1月21日、22日の卒業制作審査をもって、通っていた京都芸術大学の通信での授業は一通り終了しました。社会人芸大生ブログとしてやってきましたが、これにてこのテーマも終了となりますね。
さて、今年は人数が多くて東京管轄では41名が参加されていました。(京都はまた別に20名程度?)2日間にわたって審査会が開かれましたが、最後に先生から合格の結果を聞いたのでちゃんと終了です。これで晴れて、卒業のための単位が全て取得できたことになります。卒業制作にあたって少しまとめていますのでぜひご覧ください。

実際の卒業制作作品はこちらにまとめています。

ということで、通信制の社会人芸大生の実態と体験談についてまとめてきました。
社会人で芸大に入ろうかと迷っている方、不安を解消したい方はぜひ参考にしてください!やりたいことならば、社会人になってから、いつからでも遅くはないです。
ぜひ社会人芸大生として芸術・アートの学びの世界に一歩踏み出していきましょう!